この記事の対象者

私はあまり悩むことはありません。
すぐ悩みが出てきます。
悩みのまま行動して別の方向から解決しました。
悩むから徹底的に掘り下げて勉強して、悩みが糧となっています。
あんまり深く考えるのは苦手だけど浅くなっていないだろうか?
結局同じルートで落ち着く、何で?
このような方は、この記事を読むことで、ちょっといつもより深く考えてみて安心して今までの行動に戻ることができます。
理由は、どんな行動をとっていても一度肯定してしまうことで次の1歩が意味のあることになるからです。
悩むのは意味ない?

悩むというキーワードだけで頭が痛くなるかもしれません。
悩むのは結構辛い事です、時には結構どころじゃないほど苦しいものです。
その意味から、「悩まないで何か行動」という解決策を身に付けている人もいるかもしれません。
私も何だかわからないことに悩んで苦しんだ時があったので、悩みに対する解決策は「何か行動」ということに開き直りました。
ただ、今振り返ってみると、そこで「悩みを掘り下げる」という選択肢もあったことに気付きます。
その時は、なかなか難しいことかもしれません。
何故その時はなかなか難しいのでしょうか?
私の場合は、下知識が足りないのと、悩む理由の全体像が見えていないこと、経験が足りないことなどがありました。
また人間関係の理由もあるかもしれません。
私の現在の結論では、人間関係はうまくいく場合以外は「半々で折り合いを付ける」までしかゴールがないケースもあります。
諦めないことは大切です、ただ現時点で最終的に半分は叶わないこともあるので、そこでは悩み続けることになります。
それすらも、知識や学びで「そういうもの、という場合もある」ということを学ぶと、やはりそこ以外の選択肢も広がる可能性があり、その可能性から変わることもあります。
それでも納得いかないことはあると思います。
人間関係は知識よりもつかみどころのないものでもあり、
知識を積み重ねることで段々解決する場合もあります。

また経験からわかってきて解決してくることもあると思います。
「悩む」ことは内向的な要素
「悩む」というのは内向的よりでも外向的よりでも(両方より)でもすることだと思いませんか?
その時に「悩む」というのは内向的な要素に思います。
内向的よりの場合は、その悩みから掘り下げて糧にして、その後「あの時悩んで徹底的に向き合い勉強したり考えたり」したから、今でも生きているという場合もあるでしょう。

自分の理論などを確立しているかもしれません。
両方よりの場合は、その中間かもしれません。
学びつつ経験して段々深く広く解決していっているかもしれません。
そして外向的よりの場合は、「悩む」ことが少ないか、あまり悩まないが故に「悩む」ことも出てくるかもしれません。
そもそも「悩む」ことが内向的な要素かと思うので、外向的よりの方が悩むことが少ないかもしれません。
また外向的よりの方が「周囲がその人の悩みの種」で本人が気にしていない場合もあるかもしれません。
「本人が気が付いていないのよね」なんて陰で考えられているかもしれません。
私も外向的な要素があるようなのでわかることがあります。
「何を気にしているのかわからない」という感覚で、
「わかるように端的に伝えてほしい」という感覚があります。
外向的よりでも「悩む」こともあると思いますが、周りが気にしていることと違うことを「悩んでいる」可能性もあります。
みんなから見て「いつも気付いてくれる」というのは、戦略になります。
ここではそういうポジションをとった方がメリットが多いと思えば、「気付く事や細部に注意を払い、みんなの様子を観察し、どうなることが望まれるかを察知して、気の利く役周りをする」のです。
あるいは無難なポジションを取ります。
当たり障りなく、中くらいで捕まらないくらいのポジションをとって他のことに力を入れる場合もあるでしょう。
必ずそういう場は目的があるので、「その目的が自分のポリシーに合うか」を判断して、その目的にどんな方法でも良ければ気にならないし、気にしないと話にならない場合は気にするのです。
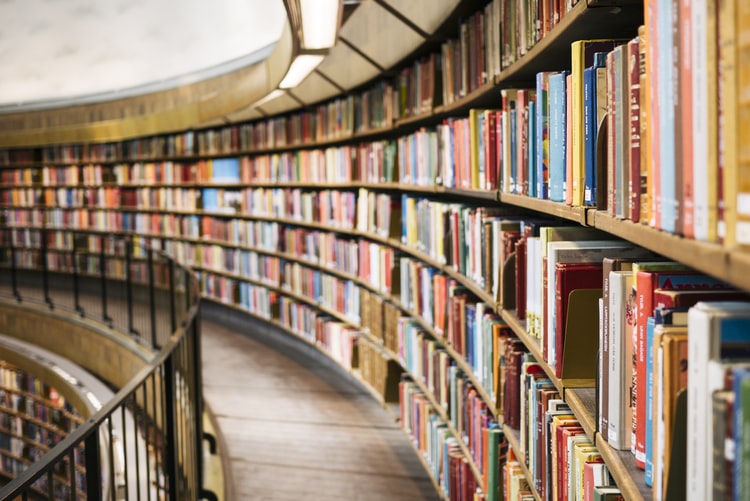
「戦略」や「気にする」というのが「内向的な要素」だと思いませんか?
外向的な人が本当に周りとの調和や、気付いてくれないことを気付いてもらうには、「端的に言葉で伝える」か周りと調和する「目的を伝える」などをして、自由に進ませれば、内向的よりの人が出来ないようなこともやってしまうかもしれません。
また「その目的」のために自分で悩みながら進むかもしれません。
それはそれでいいのではないでしょうか?
この糸口は決まりがなく、無限の可能性があるところだと思います。
悩まないで行動する!

悩みからでもそれを糧に大きく成長することを書きました。
これは誰しも「大事なこと」だとわかると思います。
しかし、悩んだからって結論が出せなかったり、悩んでいる間に具合が悪くなってもう耐えられないケースもあると思いませんか?
悩んでも無駄、何かしながら考える!
これもありだと思いませんか?
悩まなくても行動を続けていることで「解決している」ケースがあります。
「あぁ。あれね。」ということで、行動しながら「その問題を解決している」ケース。
私はこっちの方がしっくりきたタイプですが、それもありだと思いませんか?

もちろん、「悩みを糧」にするのはまた深い意味があり、「自分なりの結論が出ている」ことで様々なケースで通用する場合もあるので、
どっちから解決していくかは、人それぞれ与えられた試練であったり、自分なりの乗り越え方だと思います。
ひとつのポイントは、人によって内向的よりや両方より、外向的よりなどの得意不得意で傾向が変わる可能性があります。
ただ、どっちも魅力的な力だと思いませんか?
また、この記事では「悩み」や「勉強」を内向的な要素としてみることで、
内向的よりの方はやはり少し得意かもしれませんし、
両方よりでも「悩む」ことが成長に繋がている、
外向的でも自分を活かすために「悩みは必要だった」あるいは気が付かないけど「目的」によって悩みながらも進んでいた、など。
そして、「悩んでもしょうがない!何かやる!」これも大事なことだと思いませんか?
結局のところ、内向的よりの方が「悩み糧にした」結果、行動しませんか?
内向的よりの方もその後行動します。
行動力が上がることもあるでしょう。
今度は「行動力」はやはり外向的な要素にも感じます。
内向的よりの方が「悩みから得意な勉強」をするにしても、勉強をする!という行動が「行動力」です。
勉強中が「内向的要素」で、よし!勉強するぞ!と本や教科書を探したり読む行為が「行動力」で「外向的要素」です。
実際に勉強しているのは、小さな「行動中」の外向的要素に、「勉強」という内向的要素が入る形です。
勉強に集中できてる、勉強しながら入ってきたり考えていたりしているのが「内向的要素」です。

まだ意見も伝えない段階から「行動」しています。
研究も行動です。
まだ外向的な要素がなくても研究という「行動」をしています。
この行動は「外向的な要素」だと感じます。
両方よりの方も、考えたり学んだりしながら行動している思います。
結構、行動しないのもストレスではないでしょうか?
外向的よりの方はなおさらだと思います。
行動しないことがストレス。
つまり、内向的よりの方以外は、結構「行動しないことに耐えられない」というのがあると思うので、「行動力」は高い可能性があります。
そして、「同じ行動を繰りかえす」こともあるでしょう。
挑戦で言えば単調なのですが、スポーツやスキルを身に付けるのに、「反復練習」をしないと「弱い」もしくは「身につかない」ことがあります。
同じ行動は、最短距離ともいえます。
人は怠け者にできているので、遠回りを反復していないもので、いい方法を「反復」している場合もあります。
また、適当なことはそんなに反復できないものです。
「反復練習」をしていると新しいことも身に入りやすいことがあります。
ただ、「悩む」「考える」「勉強する」「分析する」などの掘り下げがあるから、その行動が深かったり発見があります。
これも「行動をしまくった」結果、同じ結論を出していたりもっと別の結論が出ていて、後から分析しても「凄い!」勉強では追い付かないことを成している場合があります。
また「行動しまくった」からさすがに「勉強もして」うまくいかせて経験して気付いたり。
経験値がたまってきたり。
ひとつの「行動力」をとっても小さな外向的要素をしている内向よりのパターン。
やはり、研究や勉強にしてもその量が「行動力」パワーです。
これも大切。
よく陥ることがあるケースで、
内向的よりの方(ほう)が「行動力がある」と思ってしまったり、
外向的よりの人も「そんなことまで勉強されていたのか」「人が悩まないことを悩んで乗り越えていたのか」ということがあります。
これは、ひとつの考え方で「自分の得意でないこともやった」違う要素もやることで「自分の得意な要素を活かした」という場合があります。
自分の得意な要素を生かすために、もっとうまくいくために他の可能性もある、と考えれば内向的よりでも両方よりでも外向的よりでも、まだまだ可能性が溢れているわけですね。




コメント